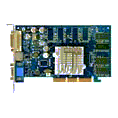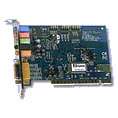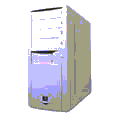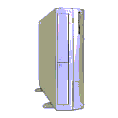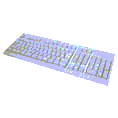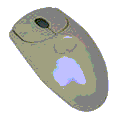|
右にあるのがCPU(プロセッサ)になります。システムボー
ド(マザーボード)に挿してあります。通常はヒートシンク、C
PUクーラーが上にかぶさっていますので見ることはほとん
どありません。ノートパソコンの場合はシステムボード(マ
ザーボード)に埋め込まれているタイプが多いためCPUの
換装(付け替え)はできないものがほとんどです。 |
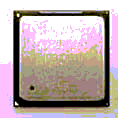 IntelCPU IntelCPU AMDCPU AMDCPU
| |
|
Intel
|
Pentium Extreme Edition(XE)
(ペンティアムエクストリームエディション)
(LGA775) |
新ロゴとともに投入されたIntelの65nmプロセス版デュアルコア「Presler」。そのPrelserを採用した最上位プロセッサ「Pentium Extreme Edition 955」。90nmプロセスのデュアルコアCPU「Smithfield」に比べると、裏面のキャパシタがずいぶんと多くなっている。FSB1,066MHz、実クロック3.46GHz、1次キャッシュはSmithfield(Pentium XE 840)と変わらず16KB×2、2次キャッシュ 2MB×2となっている。Pentium 4 Extereme Editionで1,066MHzへと引き上げたものの、Smithfieldでは800MHzに留められていたが、Preslerで改めて1,066MHz FSBへと引き上げている。CPU自体の動作クロックは、266MHz×13倍で3.46GHz。Intel 975チップセット搭載マザーボードのみ対応。945P/G、955Xでは未サポート。Hyper-Threding。EM64T、XD Bit、仮想化技術のIntel Virtualization Technologyをサポート。詳細記事は「多和田新也のニューアイテム診断室」 |
Pentium Extreme Edition(XE)
(ペンティアムエクストリームエディション)
(LGA775) |
デュアルコアの Pentium プロセッサ エクストリーム・エディションは、ハイパー・スレッディング・テクノロジを搭載し、4つのソフトウェア「スレッド」を同時に処理できる能力を提供します。製品名は「Pentium
Extreme Edition 840」。主な仕様は、動作クロック3.20GHz、FSB 800MHz、L2キャッシュ2MB(1MB×2)、コア電圧1.25〜1.388V、サーマルガイドライン130Wとなっている。製造プロセスルールは90nm、パッケージはLGA775、ステッピングはA0。機能としては、Hyper-Threadingテクノロジ、AMD64互換の64bit拡張命令「EM64T」、同社のNX機能「Execute
Disable bit」などを搭載。ほか、「This is a dual core processor.」と明記されている。ただし、デュアルコアは本来、CPU自身が各コアの調停機能を持っているが、Pentium
XEではチップセット側で調停を行なう仕様となっている。 |
Pentium D
(ペンティアムディー)
(LGA775) |
Intel初のコンシューマ向けデュアルコアプロセッサ「Pentium D」。コードネーム「Smithfield」は1個のプロセッサ上にコアを2つ搭載しています。対応マザーボードはIntel
945/955X/975チップセットとなります。仕様は、動作クロック2.80GHz〜、FSB
800MHz、L2キャッシュ2MB(1MB×2)、NXbit、EM64Tを搭載。大きな特徴としてHyper-Threadingが非搭載ということです。※PentiumD
820(2.8GHz)ではSpeed Stepテクノロジは搭載されていません。2006年3月1日に登場しているPentium
D 805版はFSB533MHz、L2キャッシュ2MB(1MB×2)です。 |
Pentium D
(ペンティアムディー)
(LGA775) |
新ロゴとともに2006年1月に投入されたIntelデュアルコアを採用したCPUが5日(木)から出回り始めた。Pentium
D 920(2.8GHz)、Pentium D 930(3GHz)、Pentium D 940(3.2GHz)、Pentium
D 950(3.4GHz)の4モデル。「Presler」は、製造プロセスを従来の90nmから65nmへ微細化したデュアルコアで、65nmのシングルコア「Cedar
Mill」2つをワンパッケージ化したものになっている。2次キャッシュは倍増の計4MB(2MB×2)を搭載する。CPUソケットは従来通りLGA775。ただし、全体の構造はこれまでと同様、単純にシングルコアを2つ載せたものであり、“真のデュアルコア”とは呼べず、「Presler」の次にくる「Conroe」でデスクトップ用のコアが“真のデュアルコア”になる予定だ。一方、ほぼ同時期に店頭に並んだモバイル向け(ノートPC向け)の最新コア「Yonah」を採用した製品は、2つのコアがバスを共有する本来のデュアルコアになっている。FSB
800MHz、L2キャッシュ4MB(2MB×2)、NXbit、EM64Tを搭載。大きな特徴としてHyper-Threadingが非搭載ということです。※PentiumD
920(2.8GHz)ではSpeed Stepテクノロジは搭載されていません。※2006年第2四半期からBIOSアップデートでEISTが有効になり消費電力が下がります。 |
Pentium4
(ペンティアムフォー:通称ペンフォー=P4)
(ソケット478) |
デスクトップパソコン、ノートパソコンに採用され、高性能パソコンの代名詞的なものです。このPentium4は大容量の電気を消費します。2GHzを超えるものは約50W、3GHzを超えるものは約80〜100Wを単体で消費します。Pentium4の中には主に3種類のコアが存在しそれぞれに特徴が違います。現在はプレスコッコアが主流ですがその前はノースウッド、ウィラメットコアが主流でした。ノースウッドコアの場合は2次キャッシュが512KBのものです。プレスコットコアの場合は2次キャッシュが1MBあります。478pinプレスコットコアの製品名はPentium4
2.8EGHzなどと表記されています。Mobile Pentium4Mはデスクトップ版Pentium4の電圧を下げて拡張版
Intel SpeedStep(R) テクノロジを搭載しバッテリーの寿命を延ばす技術が使われています。ただ、市場ではPentium Mが主力でMobile Pentium4Mはほとんど見かけません。 |
Pentium4
(ペンティアムフォー:通称ペンフォー=P4)5xx
(LGA775) |
LGA775版Pentium4が2004年5月より登場。当初の性能はソケット478版との遜色はありませんが6xxシリーズが登場し性能が若干向上しています。なお、LGA775版よりクロック周波数表示ではなくAMDが採用しているモデルナンバーを採用しています。基本性能はプレスコット版Pentium4でFSB800MHz、2次キャッシュ1MB(5xxシリーズ)/2MB(6xxシリーズ)、HTテクノロジ対応、SSE3対応となっています。Socket478版Pentium4チップセットには対応せずIntel915、925、945、955、975シリーズに対応しています。またAGPの次世代規格
PCI Express x16を搭載した製品とのセットになります。2005年11月現在、Pentium4
570J(3.8GHz)版が最上位製品となります。なお、5x1シリーズはEM64T、XDbitを搭載しているモデルになります。 |
Pentium4
(ペンティアムフォー:通称ペンフォー=P4)6xx
(LGA775) |
LGA775版Pentium4が2004年5月より登場し、2005年2月より発売されたPentium4
6xxシリーズはPentium4 5xxシリーズよりも強化した製品です。5xxシリーズとコアは同じプレスコットを採用しEM64T(64bitOS対応)、拡張版Speed
Stepテクノロジを搭載し省電力機能(3GHz→2.8GHz動作 ※2.8GHz以下に落ちることはありません。2.8GHzが最小値になります)に特化。さらに2次キャッシュを今までの1MBから2MBに強化し、セキュリティ機能を高めたXDbitを搭載しています。負荷に応じた最適な処理が行われるCPUに進化しています。対応マザーボードはIntel
915/925/945/955/975シリーズ搭載チップセット及びその互換があるVIA、SIS、nVIDIA、ATIの各シリーズに対応しています。 ※状況に応じてBIOSアップデートをする必要があります。 ※Windows
XP SP1ではXDbit、Speed Stepテクノロジは使用できません。Windows XP SP2のみでしか機能が使えないものがあります。2005年7月にはPentium4
5x1シリーズが登場し以前の5xxにEM64T対応となった新しいPentium4がリリースされています。※Pentium4
620(2.8GHz)ではSpeed Stepテクノロジは搭載されていません。2006年2月より投入された65nm版インテルPentium4
6x1シリーズはFSB800MHz、2次キャッシュ 2MBとなっています。 |
Pentium 4 Extreme Edition
(ペンティアムフォーエクストリームエディション)
(LGA775) |
現在、Pentium4シリーズの中で最強といわれるのがPentium4XEです。2003年11月に登場しました。ショップやメーカーによりPentium4EEと表記されることもあります。最新のPentium4XEはクロック周波数3.73GHzを誇りFSB1066MHz、LGA775と高性能な仕様です。詳しい記事はhttp://www.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0411/02/news004.html(IT Media)で紹介されている通りです。従来のPentium4チップセットには対応せずIntel925XEシリーズに対応しています。またAGPの次世代規格 PCI Express x16を搭載した製品とのセットになります。*これは3.46GHz版以降のもので、従来のPentium4XE 3.4GHz版以前はIntel865チップセット及びIntel910,915,925チップセット対応となります。LGA775版とソケット478版の2種類があるので注意が必要です。2005年2月に登場したプレスコットコア採用のPentium4XE 3.73GHzはFSB1066MB、2次キャッシュを2MBに増強し3次キャッシュが廃止されました。 |
Celeron
(セレロン:通称セレ=Cel)
(ソケット478) |
Intel社CPUでPentium4の高性能な技術を使用しつつ、コストパフォーマンスを追及した製品になります。一般用途(ビジネスアプリ[Office2000、XP、2003等]、デジタルカメラ編集、年賀状作成、DVDビデオなどの動画再生、2D、ひと昔前の軽い3Dゲーム、インターネット、メール等)ではPentium4と遜色なく動作します。Pentium4との最大の違いは動画のエンコード処理、処理の重たい3Dゲ−ム、CAD等の高負荷処理を行う場合にはCeleronでは満足に動作しないことです。ただし、3DゲームやCADなどはビデオカードの能力も大きく影響されるためCeleronが問題とは言い切れません。CeleronMはPentiumMの兼価版になります。性能は従来のCeleronよりも良く省電力機能を更に強化した製品になっています。 |
Celeron D
(セレロンディー:通称セレD=Cel)
(ソケット478とLGA775版の2種あり) |
CeleronCPUの進化系CPUです。2004年6月より出荷が始まったCeleronDはFSB533MHz、2次キャッシュ256kと大幅に増強されPentium4と遜色ない機能が盛り込まれています。今回からモデルナンバーに移行しています。Socket478版とLGA775版があります。XDbitが最初に搭載されたのがCeleronDです。語尾にJが付く製品がXDbitを搭載しています。 |
Celeron D
(セレロンディー:通称セレD=Cel)
(LGA775) |
Celeron D 351(3.2GHz)、346、341、336、331、326は90ナノメートルプロセスで製造され、256Kバイトの2次キャッシュ、533MHzのシステムバスを搭載。処理速度は3.2GHzでExecute
Disable Bit(XDbit)をサポート。EM64Tを搭載し64bitOS、アプリケーションを動作させることが可能。Intel910、915、925、945チップセットマザーボードに対応。※64bitOSに対応しているかはIntel公式HP参照のこと。 |
Core Duo
(コア・デュオ)
(ソケット479) |
インテル新ロゴとともに登場したモバイル向けCPUで初のデュアルコア採用製品となるIntelの「Core Duo」。プロセッサ・ナンバ「T2300」(1.66GHz)、「T2400」(1.83GHz)、「T2500」(2GHz)、いずれも2次キャッシュ容量は2MBで、2つのコアが共有するタイプとなっている。「Yonah」の開発コード名で呼ばれていた最新のモバイル向けCPUであるCore DuoとCore Soloは、対応チップセットの「Intel 945GM Express」「Intel 945PM Express」と、IEEE 802.11a/b/g準拠ワイヤレスLAN「Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection」とで、同社のモバイル向けテクノロジ「Centrino Mobile Technology」の最新モデルを構成する。従来のPentium Mと比較すると、製造プロセスが90nmから65nmに進み、FSBも533MHzから667MHzへ向上したといった特徴があるが、やはり注目はCore Duoが採用するデュアルコアパッケージだろう。Core Duoの登場によって、従来はデスクトップPCでしか利用できなかったマルチタスク環境が静音PCやノートPCなどでも利用可能になるわけだ。なお、Core Soloはシングルコア構成となっている。ちなみにCentrinoの名称は、Core Soloとのセットでは従来どおり「Centrino Mobile Technology」だが、Core Duoとのセットになると「Centrino Duo Mobile Technology」と変化する。記事はこちら 2006年3月2日にCore Duo最上位T2600を発売。スペックは製造プロセス65nm、デュアルコア、動作クロック2.16GHz、FSB
667MHz、2次キャッシュ2MB、動作電圧が最大1.3V(低クロックで動作するバッテリ最適化モード時は0.95V)。すべてSocket479。 |
Core 2 Duo
(コアツーデュオ)
(LGA775)
+
Core 2 Extreme
(コアツーエクストリーム)
(LGA775) |
Core 2 Duoは、「Conroe」チップベースのデスクトップチップと、「Merom」チップベースのノートPCチップに使用。Meromプロセッサの方がConroeチップより消費電力が少ないことを除き、両チップに違いはほとんどない。ゲーマー向け高性能プロセッサの名称は「Core
2 Extreme」。65ナノメートルプロセスで製造。業界最大の統合キャッシュとなる「Intel
Advanced Smart Cache」を備え、セキュリティ、仮想化、管理機能をプロセッサに組み込む。IntelではモバイルプラットフォームのCentrino
Duo、家庭内エンターテインメント用のViiv、企業向けのvProにもCore 2 Duoを組み込んで提供。Core
2 Duoの仕様はシステムバス(FSB)周波数 1066MHz、省電力機能“拡張版インテル
SpeedStepテクノロジー”対応、64bit拡張命令“インテル エクステンデッド・メモリ
64 テクノロジー(EM64T)”対応、ハードウェア仮想化技術“インテル バーチャライゼーション・テクノロジー”対応、データ実行防止機能“XDビット”対応、Intel
Core 2 Extreme プロセッサー X6800(2.93GHz L2 4MB TDP75W)、Intel Core
2 Duo プロセッサー E6700(2.67GHz L2 4MB TDP65W)、Intel Core 2 Duo プロセッサー
E6600(2.40GHz L2 4MB TDP65W)、Intel Core 2 Duo プロセッサー E6400(2.13GHz
L2 2MB TDP64W)、Intel Core 2 Duo プロセッサー E6300(1.86GHz L2 2MB TDP65W)
すべてLGA775、2007年4月にはE6320(1.8GHz L2 4MB TDP65W)、6420(2GHz L2 4MB
TDP65W)が登場。 |
Core 2 Duo
(コアツーデュオ)
(LGA775)
+
Core 2 Extreme
(コアツーエクストリーム)
(LGA775) |
45nmプロセスで製造される第二世代のCore 2 Duo(コードネームはPenryn(ペンリャン/ペンリン))。TDPはConroeと変わらず65W。2次キャッシュの増量(4MB→6MB)が行われている。対応マザーボードはConroe
(FSB1333MHz)と同じ。初期の製品にはコアの温度計測を正常に行なえないものがあった。型番はE8x00となる。また、モバイル用途にはT8x00(2次キャッシュ3MB)とT9x00(2次キャッシュ6MB)が存在する。 |
Core 2 Duo
(コアツーデュオ)
(LGA775) |
第1.5世代のCore 2 Duo。主な仕様は、FSBが1066MHzから1333MHzへ変更された点と2次キャッシュが4MBに統一。新チップセットに対応した点でマイナーバージョンアップとなっている。
第1.5世代はE6x50という型番で統一されている。 |
Core 2 Extreme Quad Core
(コアツーエクストリームクアッド)
(LGA775) |
Kentsfield(ケンツフィールド)の開発コードネームで呼ばれたクアッドコアCPUの「Core
2 Extreme QX6700」はCore 2 Duoのコアが2つ搭載されている製品。Core 2 Extreme
QX6700の周波数は2.66GHzとデュアルコアのCore 2 Extreme X6800よりやや低い。FSBは1,066MHz、L2キャッシュは4MB×2、TDPは130W。すべてLGA775。 |
Pentium M
(ペンティアムエム:通称セントリーノ)
(ソケット479) |
モバイルノート等に多く採用されている製品です。この製品は独自の省電力機構を備えMobile
Pentium4、Mobile Celeronよりも格段に消費電力制御のうまいプロセッサです。使用するアプリケーションによってはクロック周波数の高いMobile Pentium4Mよりも優れたパフォーマンスを発揮します。PentiumMは旧コア版(バニアス)と新コア版(ドタン)がありドタンコアはモデルナンバーで記載されています。現在のPentiumMは2次キャッシュが2MB、FSBが400から533MHzと増強され9xxチップセット対応となります。また、セントリーノは無線LAN等をすべて含んだ総称となります。 |
Celeron M
(セレロンエム:通称セレ=Cel)
(ソケット479) |
モバイルノート等に多く採用されている製品です。この製品は独自の省電力機構を備えMobile
PentiumMの技術を備え使用するアプリケーションによっては優れたパフォーマンスを発揮します。性能は2次キャッシュが512KBとPentium
Mの2次キャッシュ2MBには劣りますが従来のMobile Celeronよりもパフォーマンスの向上が見られます。チップセットはPentium
Mと同じ855GMEチップセットとなります。新Celeron Mでは2次キャッシュが1MBと増強され旧世代のPentiumMと同格になっています。Celeron
MにはSpeed Stepテクノロジは搭載されていません。 |
|
AMD
|
Phenom FX
(フェノムエフエックス)
(Socket ?) |
Phenomのラインアップは3つある。性能が高い順に「Phenom FX」「Phenom X4」「Phenom X2」。Phenom FXとPhenom
X4はCPUコアを4つ持つクアッドコアCPUで、Phenom
X2はCPUコアを2つ持つデュアルコアCPUとなる。Phenomというブランド名の由来は「驚くべき、驚異的な」という意味を持つ英単語「phenomenal」を語源としている。
共通の特徴として、従来64ビットだった浮動小数点ユニットを128ビットに強化したほか、共有型の3次キャッシュを備える。Athlon
64 FXの後継
|
Phenom X4
(フェノムエックスフォー)
(Socket AM2+) |
Athlon 64 Quadの後継。 |
Phenom X2
(フェノムエックスツー)
(Socket AM2+) |
Athlon 64 X2の後継。 |
Athlon X2
(アスロンエックスツー)
(Socket AM2) |
Athlon 64 X2の後継。 |
Athlon 64 FX Quad FX
(アスロンロクヨンエフエックス クアッドエフエックス)
(Socket F) |
開発コードである「4x4(フォー・バイ・フォー)」は、デュアルコアCPUのデュアルプロセッサ構成による4個のCPUコアと、デュアルGPUビデオカード2枚による4個のGPUを利用することにちなんだものだった。だが、最終的には4
GPUを搭載しておらずとも、規定のCPUとチップセットを利用していれば、Quad
FXを名乗れることになった模様。nForce 680a SLIチップセットのみで動作するAMD最上位CPUのひとつ。ラインナップにはFX-70(2.6GHz)、FX-72(2.8GHz)、FX-74(3.0GHz)でL1データキャッシュ64KB×2、L2データキャッシュ
1MB×2、動作電圧1.35〜1.40V、T.case(Max)55〜63度(FX-74のみ56度)、TDP125Wとなっている。このCPUに対応するメモリはDDR2
800/677/533/400 Unbuffered DIMMとなっている。 |
Athlon 64 FX
(アスロンロクヨンエフエックス)
(Socket AM2) |
Athlon 64 FXの新ソケット版。デュアルコアCPUで64bit対応。DDR2メモリー(DDR2-400/533/667/800)に対応し、より高速なメモリーによるパフォーマンス向上を実現している。ハードウェアによる仮想マシン支援機能“AMD
Virtualization”にも対応。FX-62(2.8GHz)で2次キャッシュが1MB×2.TDP125W。 |
Athlon 64 FX
(アスロンロクヨンエフエックス)
(ソケット939) |
Athlon 64 FX初のデュアルコア版。FX-60は、2.6GHz動作のコアを2つ搭載し、2次キャッシュを各コア毎に1MBを内蔵。スペックのベースとなっているのはAthlon
64 X2 4800+で、動作クロックが2.4GHzから2.6GHzへ向上している。TDP値は同じ110W。 |
Athlon 64 FX
(アスロンロクヨンエフエックス)
(ソケット939) |
AMD Athlonシリーズでもっとも高性能の部類に入るCPUです。Pentiumエクストリームエディションと遜色ないすばらしい性能を発揮します。2次キャッシュが1MBとAthlon64の512kよりも高めに搭載されています。また、FSBも1GHzと強化されています。*旧製品の場合はFSB800となります。 |
Athlon 64 X2
(アスロンロクヨンエックスツー)
(Socket AM2) |
Athlon 64 X2の新ソケット版。デュアルコアCPUで64bit対応。DDR2メモリー(DDR2-400/533/667/800)に対応し、より高速なメモリーによるパフォーマンス向上を実現している。ハードウェアによる仮想マシン支援機能“AMD
Virtualization”にも対応。Athlon 64 X2 5000+(2.6GHz L2 512KB×2 TDP89W)/4800+(2.4GHz
L2 1MB×2 TDP89W/65W)/4600+(2.4GHz L2 512KB×2 TDP89W/65W)/4400+(2.2GHz
L2 1MB×2 TDP89W/65W)/4200+(2.2GHz L2 512KB×2 TDP89W/65W)/4000+(2.0GHz
L2 1MB×2 TDP89W/65W)/3800+(2.0GHz L2 512KB×2 TDP89W/65W/35W)とラインナップされている。 |
Athlon 64 X2
(アスロンロクヨンエックスツー)
(ソケット939) |
AMD Athlonシリーズでもっとも高性能の部類に入るCPUです。ライバルのPentium
Dよりも発熱や消費電力では上回りなおかつパフォーマンスにすぐれています。2次キャッシュが1MB*2とAthlon64シリーズ初のデュアルコアCPUでFSB1GHzとなっています。モデルナンバーは3800+〜4800+となります。 |
Athlon 64
(アスロンロクヨン)
(Socket AM2) |
Athlon 64 の新ソケット版。シングルCPUで64bit対応。DDR2メモリー(DDR2-400/533/667/800)に対応。Athlon
64 3800+(2.4GHz L2 512KB TDP62W)/3500+(2.2GHz L2 512KB TDP62W/35W)の2種類がラインナップ。 |
Athlon 64
(アスロンロクヨン)
(ソケット939) |
AMD Athlon64 754pin版から939pin版に変わり更に性能向上。Pentium4エクストリームエディションと遜色ないすばらしい性能を発揮します。2次キャッシュ1MB、FSB1GHzと強化されています。コストパフォーマンスはPentium4と遜色なくオフィスアプリケーションやゲーム等に最適です。ただ、マルチタスクに関してはPentium4が若干上です。 |
Athlon 64
(アスロンロクヨン)
(ソケット754) |
家庭用パーソナルコンピュータにいち早く64bit環境を提供したCPU(プロセッサ)になります。AthlonXPやIntel社製CPUが32bitCPUに対してAthlon64は64bitCPUになります。Intel社製Penium4よりも若干性能が上です。現在、新コアと旧コアが混在している状況で同表記(例:Athlon64 3400+)で3種類がある状況になっています。新コアと旧コアの大きく異なる点はPentium4と同様にキャッシュ容量の増加点になります。キャッシュ増量によりさらに高速化、性能UPしています。現在のモデルナンバーの最上位機種は4000+です。 ※939版もあるので注意が必要です(2005/3/12現在) |
Turion 64 X2
(トゥリオンエックスツー)
(Socket S1) |
Turion 64 X2は、Turion 64のコアを拡張して、CPUコアと2次キャッシュメモリーをそれぞれ2基備えるデュアルコアCPU。ウイルスプログラムの侵入を防ぐ“Enhanced
Virus Protection”、省電力機能“PowerNow! テクノロジー”、ハードウェア仮想化技術“AMD
Virtualization”、3Dグラフィックス性能を改善する“AMD Digital Media Xpress”を搭載。DDR2-400/533/677(PC2-3200/4200/4300/5300)のメモリーに対応。90nmプロセスで製造され、内蔵するキャッシュメモリーは1次キャッシュが各コアごとに128KB(計256KB)、2次キャッシュは同じく512KBまたは256KB(計1MB〜512KB)。システムバスインターフェースは1.6GHzのHyperTransportバス。パッケージ形状は638ピンのマイクロPGAで、対応ソケットは“Socket
S1”。TDP(熱設計時消費電力)は31〜35W。今までのSocket 754よりも性能が向上。TL-60(2.0GHz
L2 512KB×2 TDP35W)、TL-56(1.8GHz L2 512KB×2 TDP33W)、TL-52(1.6GHz
L2 512KB×2 TDP31W)、TL-50(1.6GHz L2 256KB×2 TDP31W) |
Turion 64
(トゥリオン)
(ソケット754) |
モバイル向け製品が2005年3月より搭載されたのがTurionモバイルテクノロジです。90nm
SOI(Silicon-on-insulator)プロセスルールで製造され、SSE3拡張命令を新たにサポート。また、64bit
OSをサポートするAMD64や、Windows XP SP2で有効になるNX機能「Enhanced Virus
Protection」、省電力機能「PowerNow!」を搭載しています。モデルナンバーは新たな表記を採用。アルファベット2文字がCPUのクラス分けを表し、TDP(熱設計消費電力)35Wのモデルが「ML」、25Wのモデルが「MT」。2桁の数字はパフォーマンスを示すものになっています。AMD
Turion 64モバイル・テクノロジ モデルML-37、ML-34、ML-32、ML-30、MT-34、MT-32、MT-30が現在リリースされています。
|
Sempron
(センプロン)
(ソケットAとソケット754版の2種あり) |
3100+以上はSocket754版、2800+以下はSocketA版。実質Duronの後継モデルとなります。性能はPentium4と同等レベルを発揮します。新しいCPUなのでマザーボードの対応に注意が必要です。 |
Sempron
(センプロン)
(ソケット754) |
仕様は、90nm SOIプロセス、Socket 754、拡張ウイルス防止機能搭載、デュアルチャネルメモリ非対応。
64bit対応版もあります。ライバルのCeleron Dよりも一部のベンチマークテストではよい結果が出ています。 |
Sempron
(センプロン)
(ソケット939) |
AMDのバリューPC向けCPUのSempronは、これまでSocket 754版のみが発売されており、Socket
939版は今回が初となる。Socket 939版Sempronの詳細なスペックは3400+(クロック2GHz)、2次キャッシュ128KBとなっているという。CPUの表面に刻印されているOPNは「SDA3400DIO2BW」。ちなみに、Socket
754版Sempron 3400+のスペックはクロック2GHz、2次キャッシュ256KBで、2次キャッシュ容量が異なるので注意。 |
Sempron
(センプロン)
(Socket AM2) |
Sempron の新ソケット版。Socket939から進化したシングルCPUで64bit対応。DDR2メモリー(DDR2-400/533/667)に対応。Sempron
3600+(2.0GHz L2 256KB TDP62W)/3500+(2.0GHz L2 128KB TDP62W/35W)/3400+(1.8GHz
L2 256KB TDP62W/35W)/3200+(1.8GHz L2 128KB TDP62W/35W)/3000+(1.6GHz
L2 256KB TDP62W/35W)のラインナップとなっている。 |
Athlon XP
(アスロンエックスピー)
(ソケットA) |
Intel社製Pentium4プロセッサのライバル製品となるのがAthlonXPプロセッサとなります。AthlonXPはすでに1世代前のプロセッサとなりましたが現在でも多くのメーカー製、ショップブランド製を問わず採用されている製品です。ビジネスアプリケーション、3DゲームはPentium4よりも若干快適に動作してくれるのが大きなポイントになります。 |
Duron (デュロン)
(ソケットA)
|
1世代前に人気を誇ったCPUです。Athlonの兼価版になります。現在は1.6GHzが主流になります。1.4GHz以降はコアが変わり性能も向上しています。メーカー製で採用はされていないですが安価にPCを作るならコレでしょう。Office(オフィス)アプリケーションやインターネット、メールは快適に行えます。現在はSempronが後継CPUになりました。 |
| VIA |
C7 (シーセブン) |
90nm SOIプロセスで製造されるC7は、FSB 800MHz(最大)やSSE2/SSE3を新たにサポートしたCPU。動作クロックは2GHzまで対応し、最大消費電力は2GHzの場合が20W、1.5GHzの場合が12Wになるという。そのほか、Windows XP SP2のデータ実行防止機能を有効にするNX技術をサポートしている。「EPIA EN15000」(CPUクロック1.5GHz/ファン搭載)、「EPIA EN12000E」(1.2GHz/ファンレス)、「EPIA CN13000」(1.3GHz/ファン搭載)、「EPIA CN10000E」(1GHz、ファンレス) |
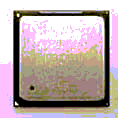 IntelCPU
IntelCPU AMDCPU
AMDCPU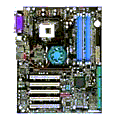
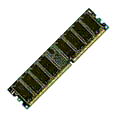 写真はDDR-SDRAMです。
写真はDDR-SDRAMです。